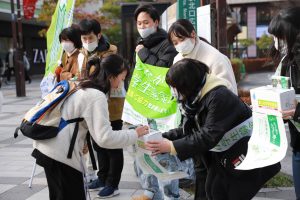心塾生インタビュー「ありがとう、愛しているを伝えなきゃ」
心塾生インタビューこころいき#1
「ありがとう、愛しているを伝えなきゃ」
ヒロキさん(大学2年生 愛知県・あしなが心塾生)
あしなが育英会の学生寮「あしなが心塾(以下、心塾)」(東京都日野市)では、日本全国、世界各国から集まった本会の大学奨学生たちが、共同生活を営んでいる。心塾には視野を広げ国際性を高めるための様々なカリキュラムがあり、奨学生の海外留学も奨励している。個性あふれる学生たちの中から、今回は、この春のウガンダ短期研修に参加したヒロキさんにお話を聞いた。
心ゆさぶられた初めての海外体験
あしなが大学奨学生のヒロキさんが初めて海外に行ったのは、東京の大学に進学した最初の年だった。
「心塾生として1年目の昨年9月、7日間のフィリピン研修に参加して、今年の3月には10日間のウガンダ短期研修に参加しました。フィリピンで初めて、海外に行きました。地元の学校や、日本企業の現地事務所や、ストリートチルドレンの地域などを訪問しました。何もかも目新しくて、ものすごく楽しかったです。でも、頑張って英語を話してみても、言葉が全然出てこなくて。それがすごく、悔しかったんです。だから、ウガンダ短期研修にはリベンジのような気持ちで参加しました。海外に出て今の自分に何が足りないか、ということに気づけたのは、本当にいい経験になったと思います」
何が足りなかったのか。英語力はもちろんだが、訪れた国々について、知らないことばかりだった。実際に現地に行くまで、フィリピンについてもウガンダについてもほとんど知識がなく、いかに自分が世界の問題に無関心に生きてきたか気付かされた。現地を訪れてからは、もっと多くを学ぶ必要性を感じた。特にアフリカは、あれほどの大陸で国の数も多いのに、歴史も文化も知らないことばかり。帰国後、ヨーロッパやアメリカに移住したアフリカ人の歴史や文化についても調べた。それは自分が大好きな、ヒップホップカルチャーの歴史でもあった。ひとつ興味を持ち始めると、派生して知りたいことが増えていく。リアルな体験からの学びは、奥が深く、幅も広いと知った。
リベンジしたウガンダで出会った子どもたちとの交流が、人生の転機に
ウガンダは特に、ヒロキさんの心を掴んだ。
「英語リベンジに加えて、ウガンダに行きたいと思ったもうひとつの理由は、心塾で一緒に暮らしている100年構想生※たちです。彼らの母国を見てみたかった。ウガンダの言語、ガンダ語はもちろん分からないし、公用語の英語も不自由しましたが、子どもたちとはサッカーや野球を通じて、言葉の壁を超えた交流ができました」
※あしなが育英会のアフリカ遺児高等教育支援100年構想事業の奨学生で、アフリカ各国から日本をはじめ世界各地に留学している大学生たち
あしながウガンダの事務所があるナンサナ市は、首都カンパラから車でおよそ30分の郊外にある、やや規模の大きな町だ。あしながウガンダが運営している施設『テラコヤ』は、主にナンサナの遺児たちを対象に基礎教育支援を行っている。
「テラコヤには野球チームがあって、みんなめちゃくちゃ野球がうまいんです。中学生くらいなのに、国際試合に行けるほどの能力と可能性があって。ただ、力があっても、お金がなくて試合に出られないという事実を知って衝撃を受けました」
ヒロキさんは、現地でサッカーボールを買って、子どもたちを遊びに誘った。彼らは夢中になって裸足でボールを追いかけた。デコボコがたくさんある空き地で蹴るため、ボールは何度もパンクしたが、子どもたちはお構いなし。足場の悪いところでも裸足で走り回る子どもたちのたくましさに驚かされた。
「学生の家に2泊3日でホームステイをさせてもらう経験もしました。ナンサナの高校やカンパラのインターナショナルスクールを見学したり、農村部にあるラカイというところの孤児院を訪ねたり。生活の格差や、見たこともない貧困状況を目の当たりにして、話したいことも聞きたいこともたくさんあったのに、言葉の壁があって、すごくもどかしかったです」
ナンサナでホームステイした家にはテレビがあって驚いた。キングサイズのベッドに子どもと4人で寝た。トイレは外に共同のものがあった。
「ホームステイ先の生活は、本やドラマで見た、昔の日本の暮らしと似ている、と思いました。電気こそ通っていますが、そんなにふんだんにあるわけじゃなくて停電もしょっちゅう。水はかめに貯めて使っていて、煮炊きは土間で、七輪のような道具を使ってやっていました」
掃除、洗濯、おつかい、水くみは、子どもたちの仕事。子どもも、労働力として頼りにされていた。
「ウガンダの子どもたちを見ていて、自分がいかに恵まれた生活をしてきたかと気付かされました」
いつか、ウガンダに戻ってきて、自分がスポンサーを探して、あの子たちを野球やサッカーの試合に連れ出したい。いつか、困りごとがあるお母さんたちに、英語やガンダ語で話しかけたい…。ヒロキさんの心の中には、それまでの人生では、考えたことも無かった思いが溢れてきた。
「自分はずっと、自分のやりたいことだけやって、金持ちになりたい、自分の将来像はよく分からないし、なるようになれ、ってことを考えていました。でも、自分は恵まれているんだと気づくと、恵まれている分、何ができるのかな?自分が学んだことが活かせるところもあるのかな?と、考えるようになったのです。自分の知識は自分だけのものじゃない、人の為に使う選択肢もあるのではないか?自分はその選択肢を取ろうかな、って。お金があると嫌なことはしなくて済みます。でも、お金を稼ぐよりも面白いことはたくさんあるのでは?と気付いたということかな」
 あしながウガンダで、テラコヤの子どもたちと
あしながウガンダで、テラコヤの子どもたちと
大好きだった父の死
「自分の家は、父が生きていたころから裕福ではありませんでした。自分は平成生まれですけど、覚えている限り茶の間にテレビは無くて、みんなでラジオを聴いていました。だから今でもラジオが好きです。おじいちゃんがドラゴンズファンで、野球中継を聞きながら晩御飯を食べるのがいつもの風景でした。ウガンダのホームステイ先にテレビがあって驚いたのには、そんな事情もあったんです(笑)」
ヒロキさんの父は、少年がそのまま大人になったような、純粋で、面白い人だったという。1級建築士で、建築業の祖父と建築事務所を経営していた。若い頃は、車高の低い車で峠道を飛ばしたり、短気でキレやすい気性だったと聞いたが、ヒロキさんが知る父親は、いつも面白くて、仕事熱心で、勉強を怠らない人。とても尊敬していた。
「父にまつわる一番古い記憶は、俺のアンパンマンの三輪車にまたがった父が、坂道をすごい勢いで下っていって、転んで鼻血を出したことです(笑)『俺流でいけ!』『熱いものは火傷するくらいがちょうどいい!』みたいなことを大声で言って、本当に火傷するような、憎めない人でした。アサヒスーパードライを飲んで、わかばを吸って、面白いことばかり言っていた父…。本当に大好きでした」
父は、何日も事務所にこもって仕事をし、自宅に帰らないことがよくあった。亡くなった時も、1週間ほど家に戻っていなかった。家族がようやく異変に気付いた時、父はすでに死亡していた。自死だった。建築業は赤字で、保険金がかけられていた。年度末の3月。ヒロキさんが小学校を卒業して、中学生になろうという春のことだ。
「子どもながらに、亡くなる前に何か父に言葉をかけられなかったのかなとか、何か行動できたんじゃないかなとか、随分と考えました。それは今でも、どこか自分の心の中に後悔として残っています」
父の死でスタートを切った中学校生活は心理的につらく、中学2年生の時には、元々が内向的な性格だったこともあって、不登校になった。中学3年生も昼夜逆転でゲームに明け暮れ、生活は荒れていく一方だった。不本意なまま、中学時代は終わった。
「危機感を抱いた母は、自分を三重県にある、全寮制の私立高校へ進学させました。生活習慣だけでもきちんと身に付けて欲しいという親心だったと思いますが、そこはやんちゃな奴らと不登校の人が集まる山奥の学校で、入ってすぐに『無理だ』と思いました」
しかし、ヒロキさんは、母を思うと簡単に諦められなかった。寮は20人の大部屋、ゲームも携帯電話もない、外部の情報は何1つ入ってこない厳しい環境。外出は月に1度だけで、先輩後輩の規律も厳しかった。何とか数週間をやり過ごしていくうちに、だんだんとそこに身を置く覚悟ができた。ヒロキさんは、毎日、野球部で汗を流し、筋トレに励んだ。気の合う友人たちとも巡り会い、先輩や先生方からも可愛がってもらえた。今振り返れば、厳しい学校で鍛えられて、有難かったと思う。
「たまに脱走する学生もいるような高校でしたが、自分はすごく楽しかったです。身体を鍛えるうちに心も強くなって、自信がつきました。高校を出たら働こうと考えていたんですけど、いつも目をかけてくれた先生が自分に大学進学を勧めてくださり、受験を考えるようになりました。高校3年生になって初めて勉強に向き合いました。今は、大学へ行って、心塾に入って、本当に良かったと思っています」
オックスフォード大学での短期留学
大学3年生になる来年度は、あしなが育英会の海外留学研修制度を利用して、再びウガンダに行きたいと考えている。1年間の長期研修プログラムに参加して、ウガンダの子どもたちの役に立ちたい。今年の夏には、ウガンダ研修参加を見据えて、英語習得のため、イギリスでの語学プログラムに参加した。
「大学のプログラムを利用して、1ヶ月弱、オックスフォード大学で英語を学びました。試験を受けて、18人の選抜チームに選ばれました。初めてのヨーロッパ、しかも世界最高峰の大学に足を踏み入れて、感じることがたくさんありました」
イギリスには、優しい人もいたが、全く無視される経験もした。英語が話せず自信の無い雰囲気を出すと、相手にしてもらえないということが分かった。カタコトでも一生懸命話をすると、相手は耳を傾けてくれた。
「クライストチャーチやセントマリーズチャーチといったキリスト教会や、博物館は無料だったから、週末になると出かけて行きました。エジプトやアフリカの美術品、日本の甲冑や浮世絵などもあって楽しかったです。それから、イギリスではお金がないほど太るということも知りました。健康的な食事は高くて、安いファストフードは太るものばかりでした」
オックスフォード大学では、1日5時間の授業を受けて、70代の女性がひとりで暮らす家にホームステイした。短期間で英語力を高めるのは容易ではなかったが、ホストファミリーのおばあさんや、その友人らと話すことで、聞く力は上達したと感じている。お年寄りたちは、時間があって忍耐強いので、会話の先生としては最適だった。
「イギリスでの1番の目標は、もちろん言語の習得でしたが、実はサッカー好きの自分としては、本場のフットボール(サッカー)を見るのも目標のひとつでした。ちょうど開幕戦をやっていて、ローカルチームの試合を見に行くことができました。スタジアムの観客が『ウオ~ッ』と大きな声を出したり、チャントと呼ばれる応援歌を歌ったり、誰かひとりが急に大きな声を張り上げると、それに他の観客も乗っかって応援が始まったりする、独特の雰囲気が楽しかったです。日本のプロサッカーの試合とは全然違いました」
 イギリスでは、サッカー観戦もできた
イギリスでは、サッカー観戦もできた
ある夜、ホストファミリーのおばあさんが、ヒロキさんに尋ねた。
「イギリスにはどうして来たの?お金を出してくれた人は、あなたに何を期待して出してくれたのかしら?」
ヒロキさんは、答えることができなかった。
「離れて暮らしているから、分からない。この間、母とは半年ぶりに会ったけれど、そういう話はしなかった」
そう伝えると、おばあさんは驚いて「No way!(それはだめよ)」と言った。
「今すぐ日本に電話しなさい。そして、お母さんと話をしなくちゃ。お父さんを亡くしているんでしょ、もっとお母さんを大事にしないと。今ある幸せを大事にしないといけないわ」
父が他界してから、ヒロキさんは、母との間に目に見えない溝のようなものを感じていた。女親だから、自分の気持ちはどうせ分からないだろう—そういう感覚もあった。中学の時は生活が荒れていたし、高校の時は気持ちが尖っていた。母もあきれていたのか、あきらめていたのか、ふたりの会話はいつもぶっきらぼうで、深い話はしなかった。たとえ、母が気持ちを伝えてくれたとしても、当時の自分は、到底、それを受け止められなかったと思う。普段は電話で話すこともなく、帰省もめったにしない。心の距離は遠かった。
おばあさんに促されたヒロキさんは、その場で日本に電話をした。日本は朝の6時だったが、電話をすると母はとても喜んでいた。ヒロキさんは、おばあさんの質問を素直に尋ねた。
「何で、俺をイギリスに行かせてくれたの?」
「私も、若いころカナダに行ったことがあって、その時にいろんな体験ができたから。あなたにも若くて時間があるときに、いろいろ体験して欲しいと思って・・・」
それを聞いたヒロキさんの目から、涙があふれた。
母が、自分に対してそんな思いを持っていたのだと知り、素直に嬉しかった。語学留学プログラムの参加費60万円は、ヒロキさんの家にとっては大きな金額だ。ヒロキさん自身もアルバイトをしたが、足りない分は、祖母と母がふたりで捻出してくれた。そのことが今更ながら有難くてならなかった。
「いつも、忙しい忙しいばかり言っててごめんね。いつも、ありがとう」
そう言って電話を切ると、ヒロキさんは子どものように泣きじゃくった。おばあさんが、優しく抱きしめてくれた。母に感謝の言葉が言えたのは初めてだった。
その後、おばあさんとは、それぞれ大切な人を亡くした者同士、心の琴線に触れる話ができた。おばあさんは、夫を亡くしていた。英語で深い話ができたことは、大貴さんにとって大きな一歩となる素晴らしい経験だった。
「これまでは、高いキャリア、高い給料が人生の目標と思っていました。でも、今は人間的に上を目指したい。人の幸せを受け止めて、与えられる人間になりたい。その前提として、自分が幸せを感じないといけないですよね」
そう語るヒロキさんの目は、キラキラと輝きながらも落ち着いている。この1年間の成長が、言葉からも、表情からもにじみ出ている。
「今日も、母に電話しようと思ってます。母に『I LOVE YOU』 を伝えなければいけないとイギリスのおばあちゃんから教わりました。自分の家族がそろっていたころの家族愛を思い出したりします。ちゃんと、『お母さん愛しているよ』を伝えます」

イギリス留学でのホストマザーと
(インタビュー 田上菜奈)
◇◇◇
ウガンダ研修から帰国したヒロキさんは、6日間かけて、心塾から300キロを歩いて帰省しました。そのときのエピソードを、あしなが高校奨学生と保護者のための進学情報サイト『あしながBASE』でご紹介しています。こちらもぜひご一読ください。
あしながBASE|フィリピン、ウガンダ、6日間の徒歩旅・・・大学に入って得たたくさんの経験
(外部リンクが開きます)