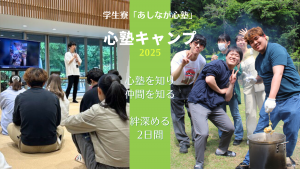シンポジウム「震災と心のケア30年~子どもの居場所とこれから~」開催
あしなが育英会は1月12日、神戸市教育会館にて「震災と心のケア30年~子どもの居場所とこれから〜」を開催しました。
本会は1995年に阪神・淡路大震災が発生した4日後から、被災地で震災遺児支援を続けてきました。今年は震災から30年の節目を迎えるにあたり、こども家庭庁・兵庫県・神戸市の後援のもとシンポジウムを開催。オンラインを含めて約100人が参加し、コーディネーターと4人のシンポジストが30年を振り返りながら今後の「居場所」について話し合いました。
登壇したのは、3歳で母親を亡くした震災遺児、現地の復興と本会の活動を追い続けてきた元新聞記者、遺児の心のケアに携わったレインボーハウス職員2人、こども家庭庁で子どもの居場所づくりに関する政策を担当する専門家です。それぞれの想いと経験をご紹介します。
大事だったのは、先輩遺児が震災遺児の最も近くにいたこと
冒頭では、一般財団法人あしなが育英会会長・玉井義臣が、オンラインで30年を振り返り挨拶を述べました。
震災直後、全国からあしなが大学奨学生やボランティアが神戸に集まり、震災遺児やその母親らのために何ができるか?を話し合いました。突如として親きょうだいを亡くすことが、いかに人生にとって大変なことか、苦しいことか。人生をあきらめるくらいの悲しみだったと思います。やはり“一番親身になれる先輩遺児が震災遺児の最も近くにいた”ことが、とても大事だったように思います。
震災から30年経ち、その間に、一生懸命、寄り添ってきたことが大きな意味を持ちました。遺児たちが心を癒され、健全に、将来に向かって前向きに歩いていけるかどうか。その道筋は人によって異なり、必ずしも一様ではありません。震災で受けた心の傷を背負いながら、まだ迷っている遺児もいるのではないかと思います。
その子への思いを持ち続けて、声を、心をかけてあげる。そして、その子が、また別の遺児家庭の弟や妹たちを励ましてくれる。時間がかかることですが、国のために非常に大事なことだと思います。私たちだけでなく、日本で少しでもそういう方々が増えて、遺児たちの居場所がある生きやすい国にするため、これからも一緒に歩んでいただきたいと思っています。

(写真左から)コーディネーターを務めた八木俊介職員、震災遺児の中埜翔太さん、神戸レインボーハウスの峰島里奈職員、神戸大学特命准教授・磯辺康子さん、こども家庭庁居場所づくり推進官・大山宏さん
“黒い虹” ー心のケアの緊急性に気づいた
コーディネーターを務めた本会会長室・八木俊介職員は、震災発生後より震災遺児のケアプログラムに携わってきました。1999年に神戸レインボーハウス完成後は館長代理として勤務。その後、あしながレインボーハウス(東京都日野市)や、東日本大震災後に設立された東北レインボーハウス(宮城県仙台市、石巻市、岩手県陸前高田市)においても、ケアプログラムやつどいの運営にあたりました。
震災直後、新聞報道などで集計した未成年の子どもがいると思われる年代の方の死者数はあまりにも多く、愕然としました。私たちは全国で街頭募金を実施し、震災遺児たちに“進学をあきらめないで”と伝え、激励金を手渡しました。
春休みに『有馬温泉のつどい』を開催したとき、ある中学1年生の女の子が、“お父さんもお母さんも地震で死んだ、私も死にたい”という作文を書いたのです。続く夏休みに行った、『海水浴かすみのつどい』では、当時10歳の男の子・かっちゃんが“黒い虹”の絵を描きました。そうしたなかで、私たちは遺児たちの異変と心のケアの緊急性に気づきました。
ケアを受ける側から支える側として参加
3歳のときに神戸市灘区で被災し、母を亡くした震災遺児の中埜翔太さん(現在会社員)は、小学1年生の時にレインボーハウスが完成してからは、ほぼ毎日のように通っていました。
職員やボランティアさんが全てを受け入れてくれました。レインボーハウスは、嫌なことがあってもノーストレスで、自分のことをさらけ出せる場所でした。心のケアを受けていたという自覚はありませんでした。
小学校を卒業したタイミングで、レインボーハウスも卒業しました。しかし、高校在学中の2008年、中国で四川大地震が起き、被災地訪問にファシリテーター役として参加することにしました。2011年の東日本大震災では、各避難所の掲示板にあしなが育英会による「特別一時金」のお知らせを貼る活動に加わりました。その後も、東日本大震災遺児との交流会には支える側として参加しています。
初動力が30年間の活動につながった
当時、神戸新聞の記者として主に災害報道を担当していた磯辺康子さん(現・神戸大学特命准教授)は、次のように語りました。
被害報道から復興報道という流れができ、その中で『心のケア』の大切さが論じられるようになりました。直後から今日まで、被災者や遺族に寄り添い伴走する存在、それがあしなが育英会だと思います。
災害が起こると多くの子どもが親を失い、支援が必要になることを、行政は全く考えていませんでした。そんななか、あしながの大学奨学生とボランティアが、新聞報道などをもとにローラー調査をして、転居先まで突きとめ、震災遺児573人を探しだしたのです。その初動力が、30年間の活動につながっていると思います。
震災遺児の恩返しが活動を推し進めた
神戸レインボーハウスで心のケア事業に携わる峰島里奈職員は、11歳の時に父親を病気で亡くし、神戸へ引っ越しました。被災したのは14歳の時でした。「(ほかの)震災遺児たちはどうしているのだろう?」という思いで、大学生のとき神戸レインボーハウスのファシリテーターとなり、その後、本会の職員となりました。
レインボーハウスは、子どもたちもボランティアさんもスタッフも、大きい家族みたいに思える温かい空間でした。遊んでいる時は、エネルギーいっぱい。でも、おはなしの時には涙を流したり、時には激しい感情を出したり…。ひとつの側面だけで、心の内がわかるものではないと教わりました。実は、子どもたちと遊んでいる大人の方が、子どもたちからもらっているものが多いと実感していました。
2003年から、受け入れ対象を広げて、震災以外の死因で親を亡くした遺児に対してもプログラムを開催するようになりました。震災遺児自身から『支援が必要なのは自分たちだけじゃない。もらった恩は返していきたい』と活動を推し進めたことが、本当に大きなことだったと思います。
子どもに「安心安全」と感じてもらえる居場所づくりを
こども家庭庁成育局成育環境課・居場所づくり推進官の大山宏さんは、2024年4月にこども家庭庁に入庁し、現在は「こどもの居場所づくりに関する指針」の普及啓発に関する事業や、調査研究事業等を担当しています。
“居場所”は、その子本人が決めるものです。大人が「ここが君の居場所だよ」と言っても、子ども自身がそう思えなければ何の意味もありません。あそこに行けば安心・安全に過ごせる、と思えば、子どもは通います。日常的に通うことができる、過ごすことができる。それを子どもが自分で選んでいる、それが“こどもの居場所”のとても大事な要件だと考えています。
居場所の役割のひとつに、地域とつながる中でその地域への愛着を育む、ということがあります。居場所づくりにおける国の政策の中では、共通する課題を抱えた子どもたちにきめ細やかに対応する場を『ターゲット的な(対象者が絞られた)居場所』、多様な子ども・若者が集まり交流することができる場を『ユニバーサル的な居場所』と呼んでいます。
心のケアは双方向性があるものですから、誰かが誰かに一方的にケアをする環境は、ほとんどあり得ません。ケアをする側にとっても日常的で、かつ何かを受け取れて、ケアすること自体が楽しければ、自然と続きます。そのような要素が、ケアを受ける側の事情にも組み込まれていくと、その活動は継続していくのではないでしょうか。

子どもと保護者の「ユニバーサルな居場所」づくりにつなげる
シンポジウムの最後には、本会会長代行・村田治(上画像右)が、次のように総括しました。
レインボーハウスは、遺児にとって居心地よく、彼らがその場所を自主的に選び、それが非常に自然な形でできる場所。そして、遺児大学生たちが真摯に寄り添い、中埜さんが言う『ケアされているとまったく気づかずに、自由にストレスを発散できる』場所です。
本日、大山さんのお話を聞いて、改めて我々は間違ってなかったと確認できました。神戸レインボーハウスでのケア経験が、東北、東京のレインボーハウスにつながっていき、全国に広がりつつあることも認識できました。
『ユニバーサルな居場所』は、こども家庭庁等を中心に考えられていくと思います。一方で、『ターゲット的な居場所』(づくり)としては、本会が阪神・淡路大震災をきっかけに初めて取り組み、次に、災害・病気遺児を中心とした居場所(づくり)へと広げてきました。これを、どのように地域とつなげていくかが一つの課題だと思っています。
本会は、東北に3つのレインボーハウスを持っていますが、当初から、10数年後に地域に寄付し還元することを決めていました。『ターゲット的な居場所』を、地域の『ユニバーサルな居場所』にする、ということを着々と進めています。
もう一点、挙げておきたいのですが。磯辺さんの発言で「子どもの居場所だけでなく、保護者の居場所も実は重要だった」
という震災当時の話がありました。
本会は昨年10月から11月にかけて、現在の高校奨学生の保護者を対象とした調査を実施しました。結果からは、貧困問題で保護者の方の経済状況が厳しくなり、そのことが子どもの心身に影響を及ぼしていることが判明しています。まさに『居場所』、つまり、子どもだけではなく『保護者の居場所』も考えていくことが重要であり、今後の課題だと考えています。
また、レインボーハウスを、各地域との関係において、その機能を広げるのか、どう拡張するのかも、一つの大きな課題です。
震災遺児の中埜さんは、「小学校6年生から中学生になるときに、レインボーハウスを卒業だ(と思った)」と仰いましたが、それは“自立”ということだと思います。中埜さんは、ケアをされる立場からは卒業で、数年後ケアをする立場になられた。そういう意味ではまさに、理想的な形でレインボーハウスが機能していたと思います。この伝統を守りながら、『保護者のユニバーサルな居場所』づくりにつなげたいと考えています。
実は、私も遺児の一人です。つらいことはいろんな形でみんなが持っていますが、『ターゲット的な居場所』だけでは、いつまでもそこから抜けられない。自分の体験を相対化できない、と思います。相対化をして、社会に一歩出ていくためには必ず『ユニバーサルな居場所』が必要になるのです。本日、そのことを確認できました。
本シンポジウムの開催は、本会にとって非常に大きな意義がありました。同時に、こども家庭庁から大山さんにも来ていただき、国の方向、そして、社会がどういう方向に向かっているのかをよく理解できました。
改めて、コーディネーターとシンポジスト、そして、ご来場ご視聴の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。