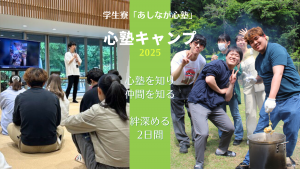4日間のつどいで決意した大学生「自分の限界を決めずに挑戦する」
2025年2月に行われた2024年度「大学・専修各種学校奨学生のつどい」(以下、つどい)で、参加者たちは、「自分が大切にしている価値観」を深掘りして自分と向き合うこと、社会課題の解決について考えることに挑戦しました。3泊4日の最終日には、つどいでの学びを踏まえて、それぞれが「大学卒業時に実現したいこと」と、「その実現のための具体的なアクションプラン(行動計画)」をまとめました。
その後、全参加者を代表して3人の学生が、自分の決意とアクションプランを閉会式で発表しました。発表全文をご紹介します。(※50音順)
奨学生のつどい開催レポートへ
当事者として、「ろう世界」の魅力を発信する

奥田さん(大学3年生・東京都出身)
私の決意は「ろう世界」の魅力を発信することです。
私は生まれつき聴覚障がい者で、両親も、兄弟も、祖父母も聴覚障がい者です。学校もろう学校でした。小さい頃は耳が聞こえないことが普通で、逆に聞こえる人のほうが珍しいと思っていたほどです。
ですが、社会に出てみると「ろう」の世界はほとんど知られておらず、多くの人が「ろう者=障がい者」としか認識していないことに気づきました。ろう者が集まると手話が飛び交う 「視覚の言語」でつながる世界になります。音のない世界ではなく、違う形で豊かにコミュニケーションをとり、聴者と異なる生き方をする世界です。
でも、ドラマや漫画では主人公のみが聴覚障害であることが多く、「ろう者はひとりだけ」になりがちで、こうした世界の日常が描かれることはほとんどありません。だからこそ、私は「ろう世界」の魅力を、何かの形で発信したいと思っています。
今回のつどいで、自分は何が好きなのか何を大切にしているのかを改めて考えました。私が一番好きなもの、それは漫画です。絵を描くことも好きなので、「登場人物全員がろう者の漫画」を描いてみたいと思いました。
また、つどいでたくさんの人と対話する中で、自分はまだ21歳で、経験も視野も広いわけではないからこそ、「対話を大切にし、いろいろな視点を知ることが重要だ」と感じました。
これを大切にしながら、つどいで学んだ 「自分の限界を決めずに挑戦する」という言葉を胸に、「ろう世界」の魅力を発信したいです。
失敗を恐れずに何事にも全力で挑戦する

鈴木さん(大学2年生・宮城県出身)
私はこの4日間のつどいを通して心に強く決意したことがあります。それは「沢山の経験をし、その経験から自分が思い描く目標に向かって失敗を恐れずに何事にも全力で挑戦する」。そして、「どんな人にとっても住みやすい空間を考えられる建築に関わる職業に就く」ということです。
私の父は14年前に倒れ、脳に重い障がいを負いました。現在でも、日常生活の中で全身痙攣が頻繁に起きているため、常に目を離せない状態です。そんな父を幼い頃から見ていた私は、生活空間が住む人にとってどれほど大きな影響を与えるか、ということを感じていました。
私は大学に入ってから建築や空間についての勉強に励んできましたが、課外活動にはあまり興味を持てず、参加したことがありませんでした。しかし、今回、つどいに参加したことは私の中で確実に良い経験になったと感じています。
同じグループの人のバッググラウンドや夢、目標を共有したことで、忙しい大学生活で曖昧になっていた「自分は誰かのために行動したい」いう気持ちを改めて認識することができました。
また、海外に住む友だちと関わることで、これまで苦手だった英語を身につけたいという想いも強くなりました。
3泊という短い期間でしたが今回のつどいを通して持っている夢が明確になるだけでなく、挑戦したいことがさらに増えました。これからも夢に向かって挑戦し続けていきたいと思います。
ブラジルの若者のために第2言語を習得する学校をつくる

ボテーリョさん(大学3年生・ブラジル出身)
私はあしなが育英会の留学プログラムを利用して、ブラジルからやって来ました。
私の生まれ育った都市は、あまり裕福ではない人たちが住む地域で、質の高い教育を受けることが難しい場所でした。
私は父が殺害された時に、自分の未来を見失ってしまいました。人とつながることが難しくなり、何年もかけて自分を立て直そうとしてきました。そして、今回のつどいに参加して、ようやく私は人とつながる機会ができたと思います。日本の若い世代である皆さんと出会い、皆さんが困難な状況でも未来に向かって努力し続ける姿に気がつきました。
私も自分について振り返り、目標を決めることができました。
このつどいで聞いた言葉が私の心に深く残っています。何かを助けるためには、自分を大事にしないといけないということです。私は今やっと過去の傷から立ち直り、ブラジルの社会に貢献できるようになったと思っています。若者たちにブラジルですでに実践している英語教育プログラムをさらに発展させて、英語などの第二言語の学校を開くことを決意しました。