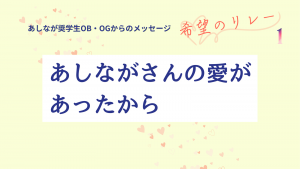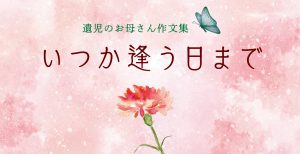松蔭高校で本会職員と奨学生が講演~生き方を考える
11月7日、兵庫県神戸市の松蔭中学校・高等学校で、本会関西エリア担当の島田北斗職員と、2人の大学奨学生が講演しました。
この講演は、2022年度から学習指導要領の改訂により導入された「総合的な探究の時間」のなかで行われ、高校3年生の生徒らに対し、遺児の現状と遺児を取り巻く社会課題の解決に取り組む本会やあしなが学生募金事務局の活動を紹介しました。
授業のテーマは「生き方を考える」。来春に卒業を控えた高校3年生の生徒たちが、これから生きていく社会で起きている問題について学び、社会の一員としてどう生きて行くかを考えることを目的にされています。
島田職員はコロナ禍が遺児家庭に及ぼしている影響や、その遺児に対して必要な支援についてを、学生の谷口さんと井川さんは、自身も親を亡くしながらも奨学金で大学に進学したという経験や、いま後輩遺児たちの進学のために取り組んでいる「あしなが学生募金」の活動についてを話しました。

母親を亡くした経験を語る谷口さん(右)とメモを取る生徒たち

井川さんは「養護教諭になることを目指して、奨学金を受けて大学に通っている」と話していた
最後に島田職員は、
今日は遺児の問題と、その問題の解決に向けて奮闘している大学生を紹介しました。遺児の問題以外にも、世の中にはたくさんの社会課題があります。しかしほとんどの問題は、見ようとしなければ見ることができません。そして、別にそれを見なくても、知らなくても毎日は過ぎていき、普通に生きていくことができます。
しかし皆さんには、見ようとしなければ見られない問題に、目を向けていってほしいのです。困っている人たちのことを思い、「なんとかしなきゃ」と考える人が社会の中に一人でも増えることが、課題解決の第一歩なのです。
と聴講した生徒にメッセージを送り、50分間の講演を終えました。
講演後、聴講した生徒から以下のような感想が寄せられました。
-
「社会問題に目を向けなくても、生きていくことができる」とおっしゃっていた島田さんにハッとさせられました。たしかに行動に移さなくたって生活はできるけど、それだと何にも社会は変わらない。だらだらスマホと過ごす時間があるなら、ボランティアをしに外へ出かけようと思います。
-
大学生の方の話を聞いて、大事な家族を失った悲しみは、今となっても大きな傷となって残るものなのだと感じました。そして、金銭的な面や進学で、私達が想像している何倍も苦しいのだと感じました。そんな中で率先してボランティアに参加して、自分と同じ苦しみを抱いている人の力になろうとする姿に、心打たれるものがありました。
-
「遺児」という言葉は聞いたことがあったのですが、その人達の抱えている問題や、働きたくてもコロナの影響等で働けない親もいると聞いて大きな衝撃を受けました。
-
まずは、遺児の家庭の現状をより多くの人が知らなければならないと思う。その現状を無視せずに、自ら目を向け、共感することで、街頭での募金に協力することが、わたしたちにできることだと思う。
今回の講演は、高校3年生という若い世代のみなさんに、遺児の現状を知ってもらえる貴重な機会となりました。
今後も社会からの遺児への理解を広めるために、講演活動を行ってまいります。